■ 家づくり豆知識
初めて一戸建て住宅を建てようと計画されている方々へ、家づくりのポイントを簡潔にまとめてみました。
これを見て、家づくりの不安が少しでも解消され、家づくりを楽しんで頂けたら幸いです。
家づくりに真剣に向き合い、じっくりと家づくりをしたい方をサポートします!
ここに記載の内容は、地域や法規の改正等により異なる場合があります。
各地域や最新の情報についてもう少し詳しく知りたい方は、メールフォームにてお気軽にご相談下さい。
ご相談は無料です!!
|
A. 家づくり費用、依頼先 |
家づくりには、様々な費用が発生します。
トータルでどのくらいの費用が必要なのかを把握しなければ、家づくりの適正な資金計画が出来ません。
ここでは、一般的な例として、木造2階建て(地下なし)、延べ面積100㎡(約30坪)の場合、トータルで
どのくらい費用がかかるのか、表にまとめてみました。
物件の条件により、かかる費用は異なりますので、あくまでも参考として見て頂ければと思います。
(費用は、下記の合計ではなく、該当する項目をご覧下さい)
|
項目 |
金額 |
説明 |
|
建築工事費 (本体工事費) |
2,400万円(仮定) |
内訳は、基礎工事、仮設工事、木工事、屋根工事、造作・家具工事、建具工事、仕上工事、左官工事、給排水衛生設備工事、空調・換気設備工事、電気設備工事、防災設備工事、タイル、石工事、塗装工事、雑工事、諸経費などです |
|
設計監理費 |
240万円前後 |
設計事務所へ依頼する場合は、設計監理契約し、お支払い時期も決定します |
|
解体工事費 |
3~5万円/坪 |
既存建物がある場合、発生します |
|
地盤調査費 |
5~10万円 |
地盤調査方法は、いくつか方法がありますが、木造住宅の場合は、SWS試験(スクリューウエイト貫入試験が一般的です。地盤の強度、地質、地盤改良の必要性を調査します |
|
測量費(確定測量) |
30~50万円 |
正式な測量図が無い場合、発生します。建築確認申請などで必要となります。確定測量は、抵当権を設定する場合や相続税を物納する土地、家を建てる予定の土地では必須です |
|
地盤改良工事費 |
30~150万円 |
地盤調査の結果次第で、発生します。採用する工法、条件などにより費用が異なります |
|
外構工事費 |
50~150万円 |
フェンス、門、植栽、カーポートなどの外廻りの工事です |
|
カーテン・ブラインドなど |
20~30万円 |
開口の大きさ、グレードによって費用が異なります |
|
(家具などの)備品 |
- |
新住居の為に新しく購入する家具などの備品で、個人差があります |
|
水道分担金 |
5~30万円 |
前面道路に埋設されている給水本管から分岐して、敷地内へ水道管を引き込み、水道メーターを設置する時に、自治体により分担金(費用)がかかります。東京都の場合は、水道分担金は不要です |
|
建築工事請負契約時の収入印紙代 |
2万円 |
建築工事請負契約は、印紙税法で定められた課税文書にあたり、収入印紙を契約書に貼り付けます |
|
住宅性能保証登録機構加入費 |
10~15万円 |
「住宅瑕疵担保履行法」で、(施工会社などの)住宅供給者に対して義務づけられています。10年間の瑕疵担保責任並びに、万が一、倒産した場合でも、一定の資金確保が保証されます |
|
設計監理契約時の収入印紙代 |
0.1万円 |
設計事務所に依頼する場合、発生します。設計監理契約は、印紙税法で定められた課税文書にあたり、収入印紙を契約書に貼り付けます |
|
ローン契約に伴う費用 |
- |
生命保険料など借入金によって費用が異なります |
|
建築確認申請手数料 |
3万円~ |
工事着工前に行います。延べ面積によって、手数料が異なります。また、申請先が民間と自治体によっても異なります |
|
完了検査手数料 |
4万円~ |
工事竣工時に行います。延べ面積によって、手数料が異なります。また、申請先が民間と自治体によっても異なります |
|
建物滅失登記費 |
4~6万円 |
既存建物を解体する場合、解体後通常1ヶ月以内に法務局へ手続きが必要です。土地家屋調査士に委任するか、所有者本人が手続きします。所有者本人で手続きの場合は3,000円前後です |
|
農地転用届出手数料 |
3~5万円 |
地目が「農地」の敷地に住宅を建てる場合、市街化区域内であれば、着工前に農業委員会への農地転用手続きが必要です。行政書士に委任するか、所有者本人が手続きします。所有者本人が手続きをする場合は、1万円程度ですが、通常は、(不動産屋などの)売主負担となります |
|
農地転用許可申請手数料 |
7~10万円 |
地目が「農地」の敷地に、住宅を建てる場合、市街化区域外であれば、都道府県知事または、農林水産大臣の許可が必要です。行政書士に委任するか、所有者本人が手続きします |
|
地目変更登記費 |
5~6万円 |
地目が「宅地以外」の敷地に、住宅を建てる場合、(宅地造成し)宅地に変更した日から1ヶ月以内に、法務局にて「宅地」への地目変更登記を行います。土地家屋調査士に委任するか、所有者本人が手続きします |
|
建物表示登記費 |
8~12万円 |
新築し、完成してから1ヶ月以内に法務局へ手続きが必要です。土地家屋調査士に委任するか、所有者本人が手続きします |
|
所有権保存登記費 |
3~5万円 (登録免許税含む) |
所有権保存登記をする事によって、売買、相続、抵当権の設定が可能になります。司法書士に委任するか、所有者本人が手続きします |
|
所有権移転登記費 |
20~40万円 (登録免許税含む) |
前の所有者から不動産を譲り受けた場合に、手続きを行います。司法書士に委任するか、所有者本人が手続きします |
|
抵当権設定登記費 |
8~15万円 (登録免許税含む) |
債権を保証するための担保の設定です。金融機関で住宅ローンを組み、一戸建てを購入した場合、通常その住宅の土地と建物には、抵当権が設定されます。司法書士に委任するか、所有者本人が手続きします |
|
近隣挨拶 |
0.1~3万円 |
着工前や引越し後、\1,000/件を目安に、菓子折りやタオルなどを用意して、近隣へご挨拶に伺います |
|
地鎮祭費用 |
4~6万円 |
地域の神主に依頼します。神主さんへ支払う金額は、2~3万円が目安で、式が終了後、のし袋に入れて渡します。のし袋には、「玉串料」または「初穂料」と記入します。また、「供え物」は、通常神社側で用意しますので、セットで4~6万円です |
|
上棟式費用 |
10~30万円 |
土台が出来上がり、柱、梁、桁などの骨組みが完成した後、棟木を棟に上げる時に行います。地鎮祭と異なり、通常は神主さんに来て頂く事が無い為、現場監督が式を進める事がほとんどです。職人さんへのご祝儀(\5,000~\20,000程度)、料理、引き出物などを用意します。最近では、上棟式を省略するケースが増えています |
|
工事中の仮住まいへの引越し費用、家賃 |
50~100万円 |
建て替えの場合などで発生します。費用は、仮住まいの場所や、大きさなどによって異なります |
|
新居への引越し費用 |
5~10万円 |
引越し業者や、運搬量、距離などによって費用が異なります |
|
火災保険料 |
2~3万円/年 |
ローンの借入年数を限度とし、期間に応じて金額が異なります |
|
地震保険料 |
2~5万円/年 |
通常は、火災保険とセットになり、保険金額は、火災保険の30~50%になります。地震保険料控除については、税務署へ確認して下さい |
|
不動産取得費 |
不動産評価額×3% |
(土地や家屋の)不動産を取得した日から30日以内に、土地、家屋の所在地を所管する(都道府県)税務署へ申告する必要があります。但し、相続により取得した場合は、課税されません。軽減措置があるので、税務署へ確認して下さい |
|
固定資産税 |
- |
毎年1月1日時点の所有者に課税されます。市町村(東京23区においては東京都)が課税する税金です |
|
都市計画税 |
- |
毎年1月1日時点の所有者に課税されます。市街化区域内に所在する土地及び家屋が対象資産で、固定資産税と合わせて納めます。軽減措置があるので、税務署へ確認して下さい |
家づくりをする上で、依頼先選びは非常に重要なポイントです。
満足な家が出来るかどうかは、依頼先選びでほとんど決定してしまうと言っても過言ではありません。
しかし、どこに依頼した方が良いのか分からない人が多いと思います。
そんな建築主さんへのヒントになればと思い、家づくりの依頼先の種類とその特徴を簡潔に説明します。
依頼先のコストの比較はここでは触れていませんが、A-005. 設計料って本当に高いの?に記載されていま
すのでそちらをご参照して下さい。
□ 設計事務所
設計事務所は、一般的に、設計と工事監理を専門としています。
建築主さんの直接的又は潜在的なご要望を理解し、基本図から詳細図まで描きます。
その図面を基に、建築主さんの希望する施工会社や、設計者が選定した施工会社で相見積(単独もある)し、
厳しく査定した上で、施工会社を決定します。
工事中は、図面通り工事が行われているか工事監理をします。
こうして完成した住宅は、建築主さんの思いと設計者のデザイン力や技術力が合わさり、個性的な住宅となる
場合が多いようです。
家づくりに時間をかけ、じっくりと取り組む建築主さんに向いていると思います。
一方、家づくりにそれほどこだわりがなく、とにかくスピーディーに進めたい建築主さんには不向きかもしれ
ません。
□ 工務店
工務店は、大小さまざまありますが、家づくりにおいては、地域に密着した施工会社と言えます。
建築主さんの希望を反映させた基本図を(社内又は外注の設計者が)作成し、施工します。
それに基づき施工します。
何かあった時に、近所なのですぐに対応してくれる安心感を求める建築主さんに向いていると思います。
一方、工務店により、技術力やアフターメンテナンスの対応方法などに差があるので、その工務店の実績や、
評判を参考にしつつ依頼する方が良いと思います。
□ ハウスメーカー
ハウスメーカーは、一般的に、仕様やデザインなどがシステム化されており、技術力は安定し、スムーズに家
づくりが出来る特徴があります。
建築主さんが選んだ仕様やデザインのパターンを組み合わせて、基本図を(社内又は外注の設計者が)作成し
、施工します。
とにかくスピーディーに家づくりをしたい建築主さんに向いていると思います。
一方、ハウスメーカーの仕様やパターン以外を選定すると、納期が遅れたり、コストアップもある様です。
また、こだわりのある住宅を求める建築主さんにとっては、少し物足りない場合があるかもしれません。
設計事務所を知る機会は、友人・知人が建築士、友人・知人の紹介、TV、雑誌、インターネットなどがあり
ますが、その中でも、インターネットで知る機会が最も多いと思います。
インターネットで検索して見ると、実に多くの設計事務所があり、どこを選んで良いか迷ってしまいます。
そんな時、自分がどんなタイプの建築主なのかという事を念頭において、設計事務所を選ぶのもひとつの方法
だと思います。
A. じっくり時間をかけて理想の家をつくりたいタイプ
事務所設立後5年程度以内、作品実績が少ない、近所であるなど、建築主さんと時間をかけて向き合える設計
事務所がお勧めです。
B. 人に自慢出来るような素敵なデザインの家をつくりたいタイプ
(30、40歳代の)比較的若い建築士、住宅専門または店舗設計の実績がある、TV・雑誌で知られているな
ど、アトリエ系の設計事務所がお勧めです。
C. 建築士に家づくりをほぼ全ておまかせしたいタイプ
事務所設立後5年以上、作品実績が多数あるなど、忙しい建築主さんの代理として安心出来る中堅からベテラ
ンの設計事務所がお勧めです。
D. デザインにそれほどこだわりがなく、欠陥の無い堅実な家をつくりたいタイプ
アトリエ系以外の全ての設計事務所がお勧めです。
(アトリエ系が堅実ではないという意味では無く、コストバランスを考慮した上でのひとつの考え方です)
E. とにかくローコストで家をつくりたいタイプ
分離発注、特殊な工法に対応出来る技術派の設計事務所がお勧めです。
以上列記しましたが、建築主さんと同様、設計事務所にも(上記に当てはまらない)様々なタイプがあり、一
概には判断出来ません。
家づくりは、建築主さんと設計者との相性がとても重要です。
相性は、実際に会って話してみなければわかりませんし、それなりの時間が必要です。
上記は、(設計者と会う前の事前情報)として、ご参考にして頂ければと思います。
施工会社を選ぶ際、親戚や知り合いの工務店、モデルハウスで好印象だったハウスメーカーなどに依頼するケ
ースがあります。
余計なお世話かもしれませんが、折角の施工会社を選ぶ権利をもう少し生かして欲しいと思います。
専門的な知識を持っている建築主さんであればともかく、可能であれば、設計事務所を利用(※)した方が、
施工会社選びに失敗する危険性は少ないと思います。
施工会社から提出された図面や見積書、工事中のチェックなどを建築主さん自身が的確に行うのは、非常に難
しい事だと思います。
もし、(設計事務所に依頼せず)施工会社へ直接依頼する場合、その工務店やハウスメーカーが、信用出来そ
うだと思っても、特命(単独)で選ぶ事は、避けた方が無難です。
手間はかかりますが、本命以外の施工会社1~2社に声を掛け、各社にプランと見積書を提出して頂きましょ
う。
これを「相見積もり(あいみつもり)」と言いますが、「相見積もり」をする事によって、各施工会社に競争
意識が芽生え、少なくとも工事費の面ではコストダウンに繋がりやすくなります。
「相見積もり」に参加する各社には、見積もりを依頼する段階で、「相見積もり」となる事を伝えておけば、
見積もりの結果、お断りする場合であっても、マナー違反にはなりません。
(※)図面作成、施工会社の候補選び、相見積もりの為の図面説明会の開催、見積書のチェック、施工会社の
選定、工事の監理などは、設計事務所に任せる事が可能です。
「設計料って高いから家では建築家には頼めないね」とか、「設計料を払う分、仕様をグレードアップ出来
る」などの話を聞いた事があります。
本当にそうでしょうか?
これから先の話は、マイホームの依頼先を考える際に、参考になればと思って記載しますが、決してハウスメ
ーカーや工務店を批判している訳ではありません。
依頼先を考える時、購入した家に合わせて生活するか、生活スタイルに合わせた家に住みたいかによって判断
する事が重要だと考えます。
通常、前者の場合、ハウスメーカーや工務店、後者の場合、設計事務所という事になると思います。
ここではまず、設計事務所へ依頼する場合とハウスメーカー、工務店へ依頼する場合のイメージを簡潔に説明
致します。
□ ハウスメーカー、工務店へ依頼する場合のイメージ
(設計費及び工事費の)お支払いを一本化出来ます。
①図面チェックは、許認可で必要な基本図をもとに、建築主とハウスメーカー又は工務店と行います。
②見積チェック、③工事チェックは、建築主さん自身で行います。
規格型住宅の場合は、(設計の手間が少ないことや、取引先の固定化などで)スピーディです。
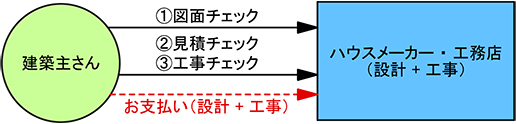
□ 設計事務所へ依頼する場合のイメージ
(設計費及び工事費の)お支払いは、別々となります。
①図面チェックは、基本図及び詳細図、模型、サンプルなどで、建築主さん自身及び設計事務所と詳細までつ
めて行います。
②見積チェック、③工事チェックは、設計事務所が建築主さんの代理として行います。
設計事務所は、家づくりの専門家として建築主さんのパートナーとなり、施工会社の間に入ってサポート致し
ます。
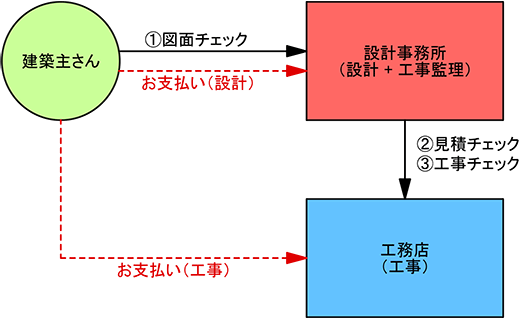
さて、本題に入り、設計料は本当に高いのか?
それは、工事費全体の内訳から判断する必要があると思います。
以下に、設計事務所、ハウスメーカー、工務店へ依頼した場合それぞれについて、工事費の内訳イメージを簡
潔にまとめました。
設計事務所の立場から設計料が高いか安いかを判断する事は、公平ではなく意味がありません。
この内訳を見て頂き、本当に設計料が高いのか、各自でご判断して頂ければと思います。
□ 設計事務所へ依頼した場合の工事費
許認可に必要な最低限の図面と詳細な図面の作成や、見積チェック、工事監理などで、設計監理料は上がりま
すが、設計事務所が工事費を厳しく管理しますので、工務店の利益は減ります。
|
建物原価 |
工務店利益 |
設計監理料 |
□ 工務店に依頼した場合の工事費
設計は工務店自社もしくは外注し、(例外はありますが)許認可に必要な最低限の図面だけであるのと、第三
者による監理の部分がなくなるので、設計料は下がりますが、工事費は工務店自身で管理するので、工務店の
利益は上がります。
|
建物原価 |
工務店利益 |
設計料 |
□ ハウスメーカーに依頼した場合の工事費
設計はハウスメーカー自社もしくは外注し、(例外はありますが)許認可に必要な最低限の図面だけであるの
と、第三者による監理の部分がなくなるので、設計料は下がりますが、工事費はハウスメーカー自身で管理す
るので、ハウスメーカーの利益は確保出来ます。
また、広告、CM、モデルハウスなどによる広告宣伝費や、規格型住宅の技術開発費などが工事費に含まれま
す。
|
建物原価 |
広告宣伝費 研究開発費 |
ハウスメーカー利益 |
設計料 |
個人住宅のような一般的に小規模な建築物であれば、法規的(建築士法)には、建築士の資格を所有していな
い建築主さん自身でも、設計及び工事監理をする事が出来ます。
やる気、根気、時間、建築の知識が必要ですが、建築主さん自身が主体となって、設計図書の作成、確認申請
、工事会社の手配、工事費のチェック、工事監理等を行ない、理想のマイホームを手に入れる事は可能です。
不安であれば、もちろん、設計事務所にアドバイスを求めて頂いても喜んでお受けさせて頂きます。
建築士でなくても設計及び工事監理が出来る範囲は、下図(A赤い部分)をご参照下さい。
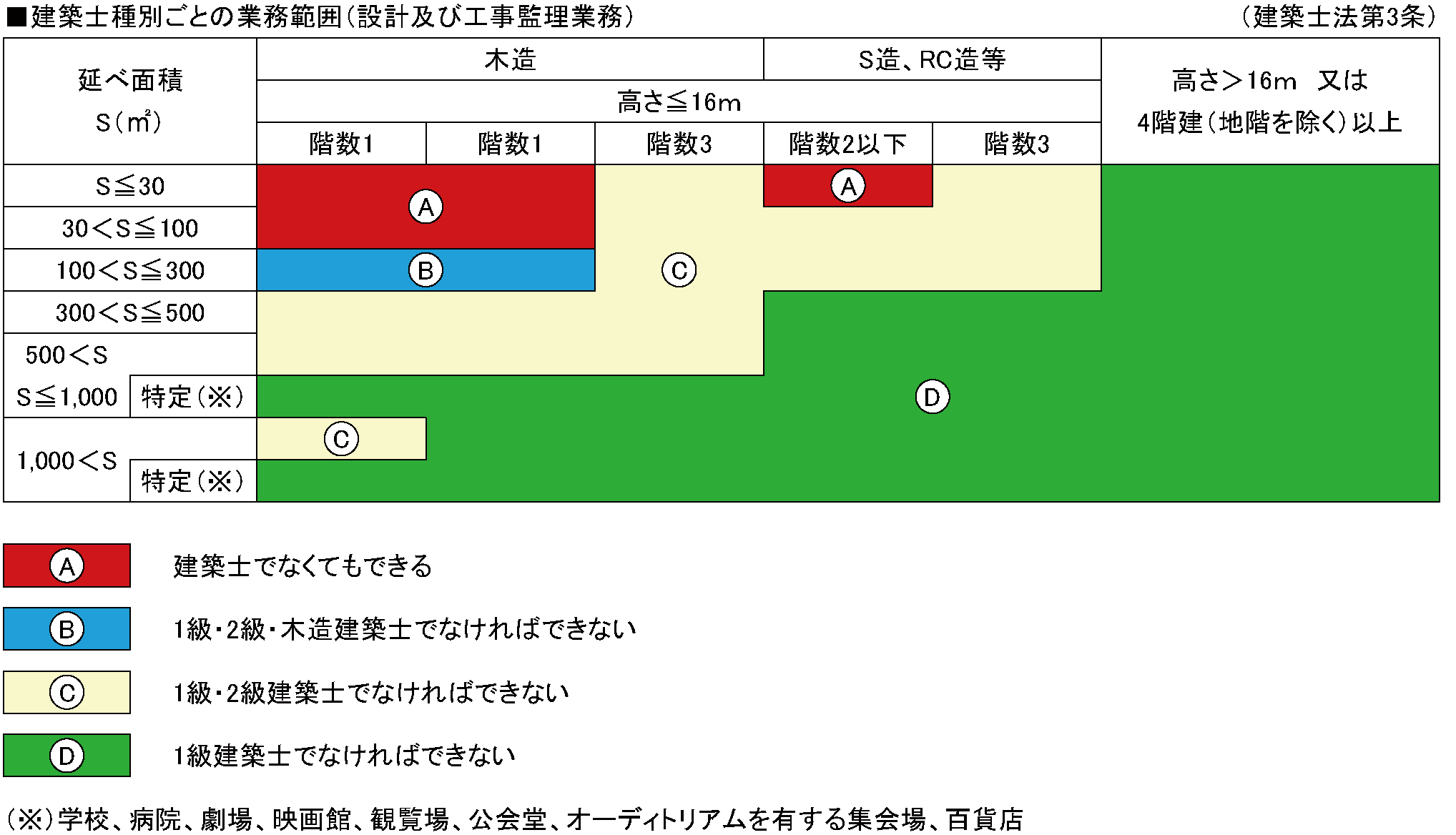
設計図書と施工者がいれば「工事監理」は必要ないのでは?と聞かれる事があります。
確かに建物は完成するでしょう。
しかし、「工事監理」が必要な事は、法律で明確に定められているのです。
<建築基準法第5条の6第4項>
建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条(中略)に規定する建築士
である工事監理者を定めなければならない。
そもそも、この建築基準法と建築士法の目的は何か?
それぞれの第1条に記述されています。
<建築基準法第1条>
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産
の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
<建築士法第1条>
この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建
築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
これらの目的を達成する為に、工事監理者はどうやって業務を遂行するのか?
建築士法第2条に定義が記述されています。
<建築士法第2条第8項>
この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおり
に実施されているかいないかを確認することをいう。
これらから、「工事監理」はやっぱり必要だと思って頂ければと思います。
Copyright(C)2008-2025 Noboru Nagaoka Architect.All rights reserved.
