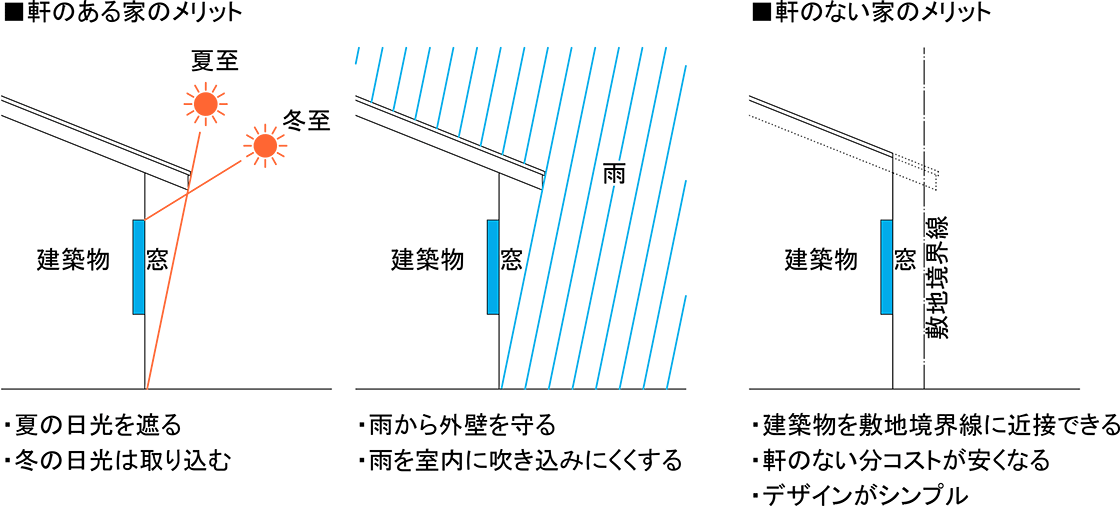■ 家づくり豆知識
初めて一戸建て住宅を建てようと計画されている方々へ、家づくりのポイントを簡潔にまとめてみました。
これを見て、家づくりの不安が少しでも解消され、家づくりを楽しんで頂けたら幸いです。
家づくりに真剣に向き合い、じっくりと家づくりをしたい方をサポートします!
ここに記載の内容は、地域や法規の改正等により異なる場合があります。
各地域や最新の情報についてもう少し詳しく知りたい方は、メールフォームにてお気軽にご相談下さい。
ご相談は無料です!!
|
D. 建築技術、しくみ |
電気は、道路に設置した電柱上部の電線から引き込む架空配線が一般的です。
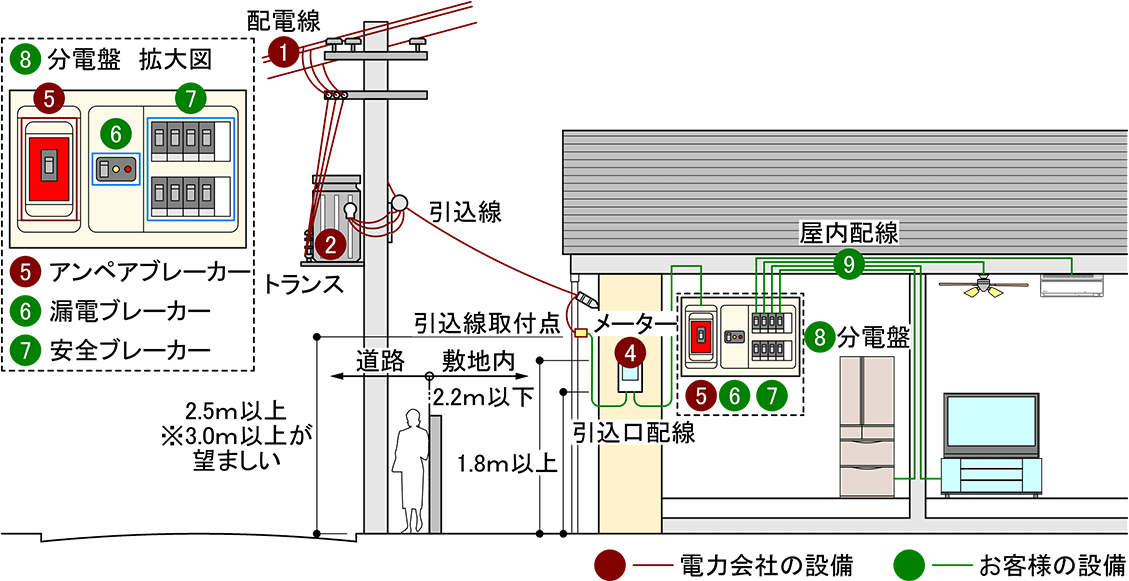
(黄または赤のチューブが設置してある)引込線取付点が、お客様と(東京電力などの)電気会社の境界(保
安責任、財産の分界点)になります。
東京電力の規定で、引込線取付点の高さは、2.5m以上(3.0m以上が望ましい)、電気メーター(電力量計
)の設置高さは、下端で1.8m以上、上端で2.2m以下と定められています。
水道設備の給水方式には、主に以下の3種類の方法があります。
① 配水管からの水圧で給水する直圧直結給水方式
② 増圧ポンプにより給水する増圧直結給水方式
③ 貯水槽に貯めて給水する貯水槽水道方式
住宅などの2階建て(もしくは3階建て)以下の建物では、通常、①直圧直結給水方式が採用されますので、
以下はその説明をします。
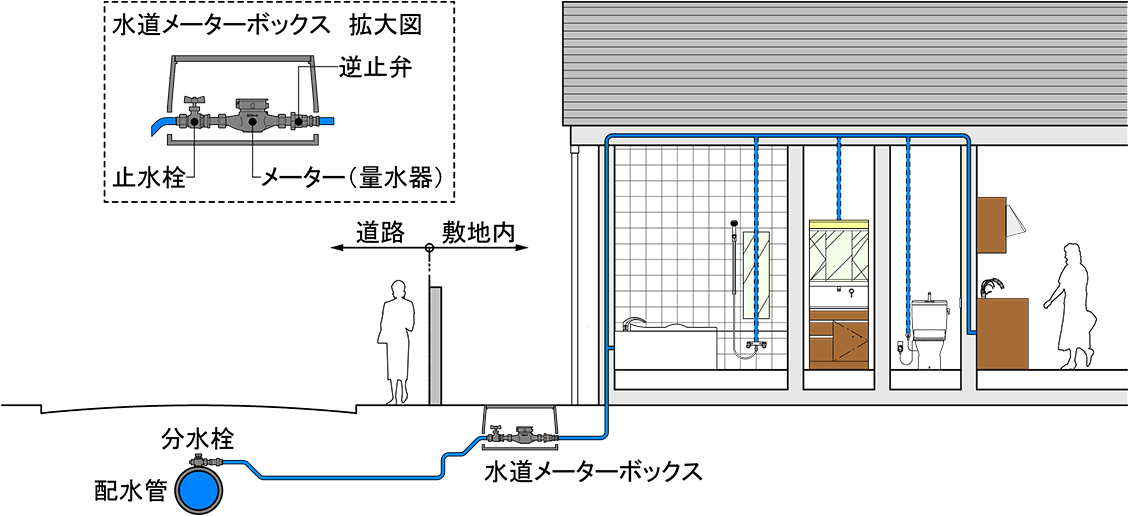
東京都などでは、配水管の分岐部分(分水栓)から蛇口までは、建物所有者が設置したものであり、お客様
の財産になります。
よって、(水道メーターを除く)その部分の維持管理は、お客様で行う事になっています。
水道メーターについては、自治体からの貸与となります。
分水栓から最初の止水栓までは、自治体所有となる地域もあり、所有区分については、各自治体に確認する
必要があります。
各家庭などから出た(浴室、洗面、トイレ、キッチンなどの)汚水や、雨水は、枡を通じて道路内に埋設さ
れた下水道管へと流れていきます。
汚水と雨水を流す方式は、下図のような合流式と分流式の2種類があります。
□ 合流式
汚水と雨水を一緒の管で水再生センターまで流します。
東京都などの比較的以前から下水道に着手した都市は、合流式下水道が多く採用されています。
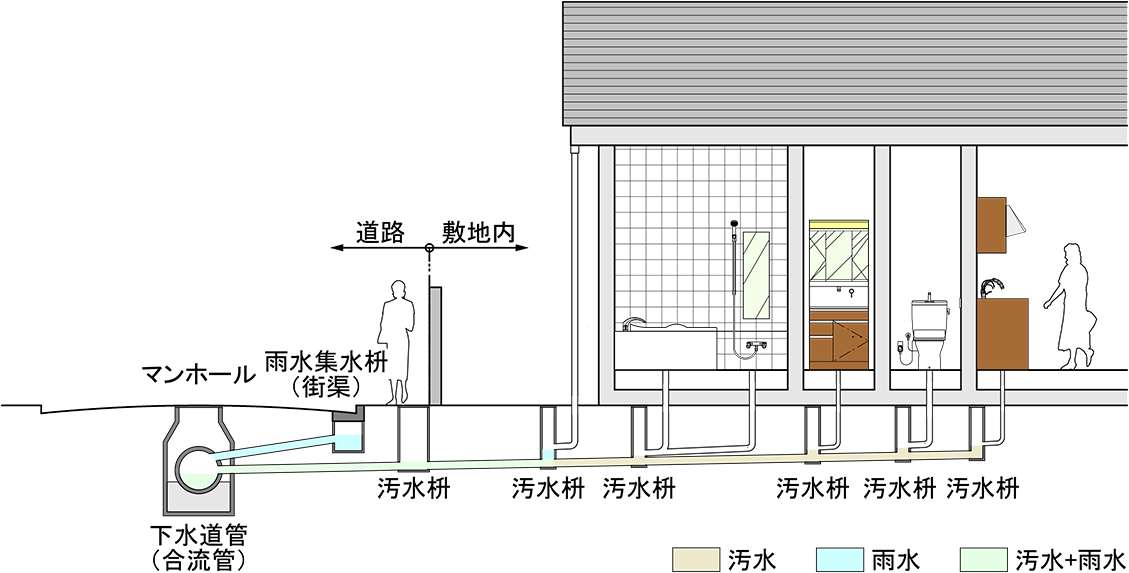
□ 分流式
汚水と雨水を別々の管で流し、汚水は水再生センターへ、雨水はそのまま川や海へ流します。
昭和40年代以降は、多くの都市で分流式下水道が採用されています。
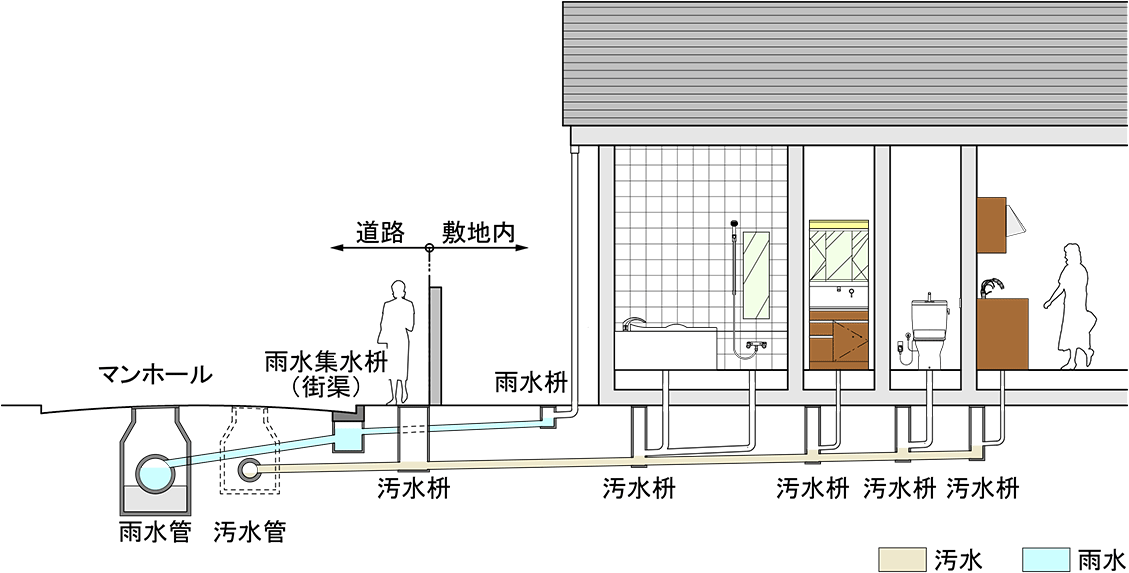
住宅の基礎は、直接基礎(布基礎、ベタ基礎)と杭基礎があります。
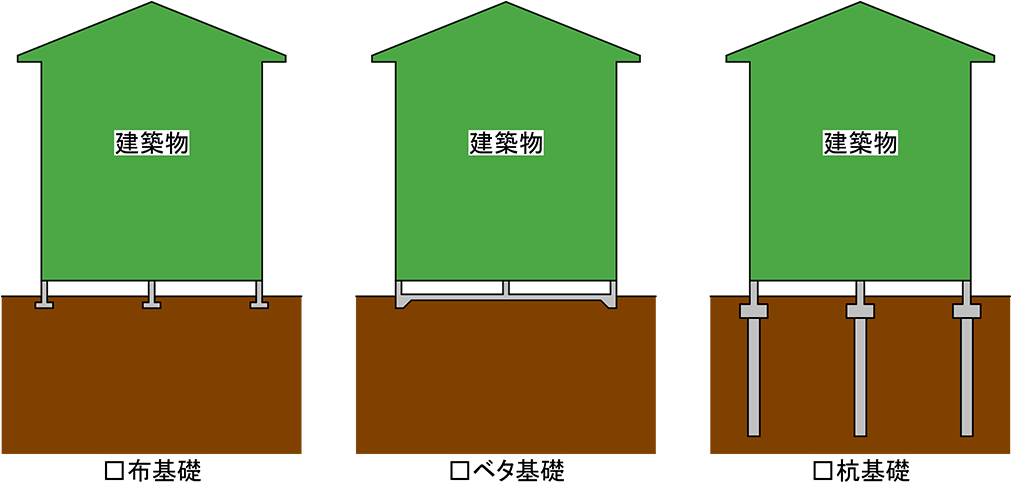
□ 布基礎
布基礎は、地耐力が30kN/㎡以上の地盤に採用され、建築物の土台に沿って連続した帯状の基礎で建築物を
支える工法です。
□ ベタ基礎
ベタ基礎は、地耐力が20kN/㎡以上の地盤に採用され、底部が1枚板状になっており、面全体で建築物を支
える工法です。
□ 杭基礎
杭基礎は、地耐力が20kN/㎡未満の地盤に採用され、地中深くまで杭を打ち込む事によって建築物を支える
工法です。
建築基準法では、下表のように地盤の強さ(地耐力)によって使用出来る基礎の種類が定められていますの
で、基礎の選定は、(SWS試験などの)地盤調査によって得られた地耐力に基づき、適切に基礎の選択をす
る必要があります。
|
地盤の地耐力 |
20kN/㎡未満 |
20kN/㎡以上30kN㎡未満 |
30kN/㎡以上 | |
|
直接基礎 |
布基礎 |
× |
× |
○ |
|
ベタ基礎 |
× |
○ |
○ | |
|
杭基礎 |
○ |
○ |
○ | |
また、異なる構造の基礎を併用する事は禁止されています。
何らかの事情で異なる構造の基礎を併用する場合は、構造計算によって、構造耐力上の安全性を確認する必要
がありますので注意して下さい。
一般的な住宅の構造は、大きく分けて木造、鉄骨造(S造)、鉄筋コンクリート造(RC造)の3種類ありま
す。
2階建て住宅(20坪~40坪)を想定し、それぞれの構造ごとに簡潔に下記にまとめました。
あくまでも目安としてご覧下さい。
|
|
木造 |
鉄骨造 |
鉄筋コンクリート造 |
|
特徴 |
床、壁、梁、柱などの構造部分に木材を使用した構造。 日本人馴染みの構造であり、個人住宅の主流となっている |
床、壁、梁、柱などの構造部分に鉄材を使用した構造。 ハウスメ-カーによるプレハブ住宅は定着している |
床、壁、梁、柱などの構造部分に鉄筋とコンクリートを使用した構造。 個性的な住宅が楽しめる |
|
標準工期 |
3~5ヶ月 |
プレハブ(軽量鉄骨)の場合 2~4ヶ月 重量鉄骨の場合 3~5ヶ月 |
5~7ヶ月 |
|
建築工事費 |
80万円/坪~ |
90万円/坪~ |
100万円/坪~ |
|
耐震性 |
鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比較すると弱い |
柔構造なので揺れるが、比較的地震に強い。 ゆらゆら揺れる柳の木のイメージ |
剛構造なので揺れにくく、地震に強い。 しっかりと根を張った桜の木のイメージ |
技術は日進月歩し、ガラスの種類は多岐に渡りますが、ここでは、住宅で外壁サッシに一般的に使用されるガ
ラスの配置方法である単板ガラス、ペアガラス、複層ガラスの特徴を簡潔に説明します。
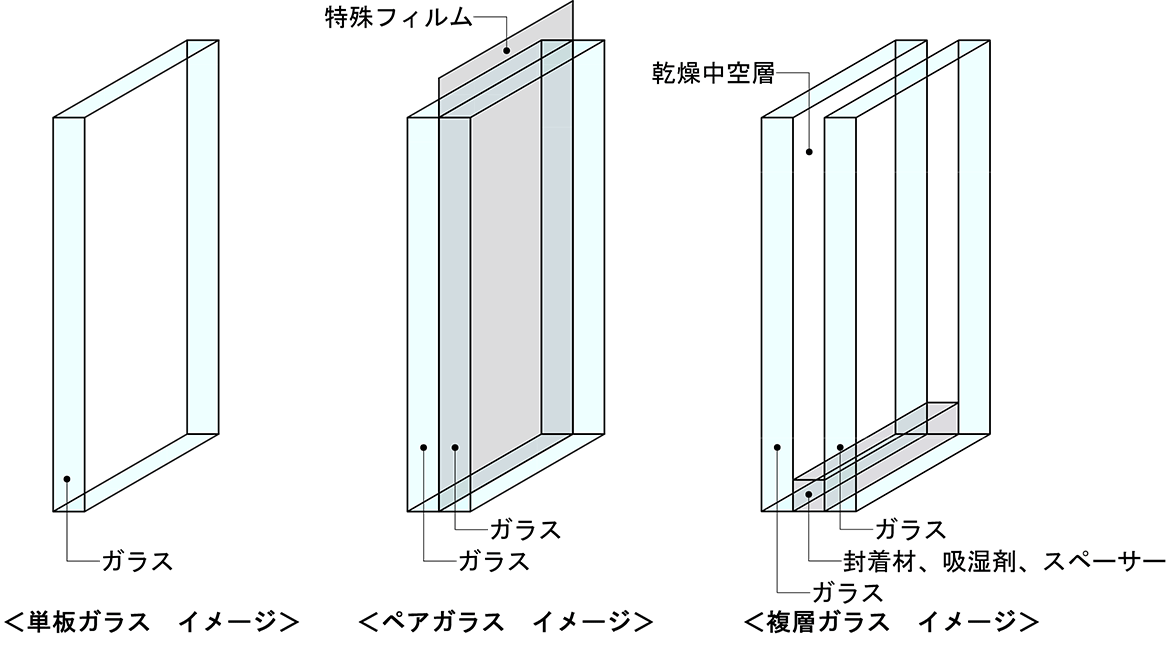
|
ガラスの配置方法 |
特徴 |
|
単板ガラス |
住宅サッシで昔から使用されている。外部と室内の温度差が大きいと結露が発生しやすい。1枚なのでコストは安いが比較的割れやすい |
|
ペアガラス |
ガラスとガラスの間に特殊フィルムを挟むので、割れにくく、破片が脱落しづらい。防犯性が優れている |
|
複層ガラス |
ガラスとガラスの間に空気層があるので、断熱性が優れ、結露が発生しづらい。省エネ基準適合の標準仕様である |
コンセントは、使用する用途に合わせて選ぶ必要があります。
ここでは、住宅で使用される代表的なコンセントを記載します。
■ 一般用コンセント
掃除、携帯電話の充電などで使用されるコンセントです。
一般コンセント



■ PC、一般用コンセント
パソコンなどで使用されるコンセントです。
抜け止め式コンセント


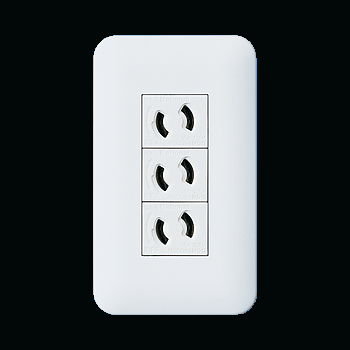
OAタップ
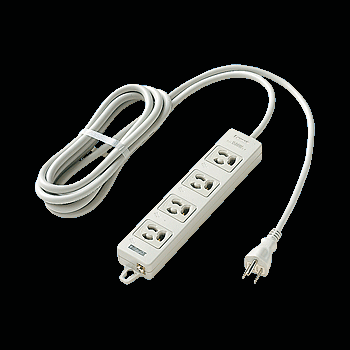
■ 家電、水廻り機器用コンセント
冷蔵庫、洗濯機、ウォシュレット付便座などで使用されるコンセントです。
アースターミナル付コンセント
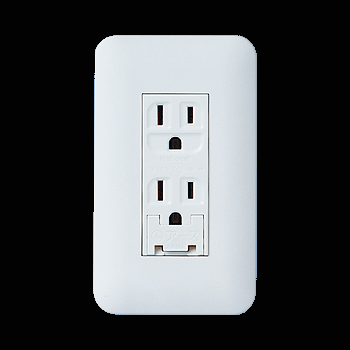
■ エアコン、電磁調理器用コンセント
エアコン、電磁調理器などで消費電力が1000Wを超える高電力用のコンセントです。
アースターミナル付接地コンセント

■ つまづき防止コンセント
コンセントがマグネットでくっつく仕様になっているので、コードに足を引っ掛けてもポロッと外れます。
幼児、高齢者、体の不自由な人の転倒防止用として有効です。
マグネット式コンセント

■ 通信情報一体化コンセント
電源、(TEL、LANなどの)通信、(TVなどの)情報を一つにまとめたコンセントです。
マルチメディアコンセント
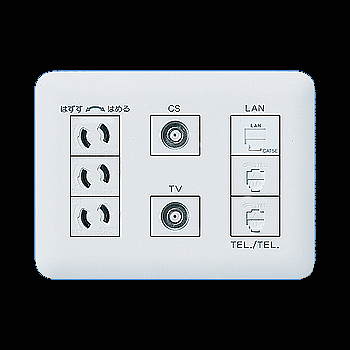
■ 床用コンセント
普段は床下に収納されていて、必要に応じて差込口を取り出して使用するコンセントです。
アップコンセント
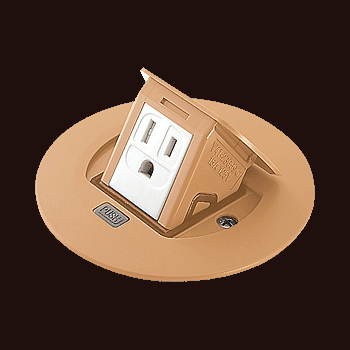
■ 屋外用コンセント
バルコニーや庭先などの屋外で使用されるコンセントです。
笠が付いており、雨水が浸入しにくくなっています。
防水コンセント

給水、給湯、排水、ガス、電気で用いられる代表的な配管をまとめました。
■ 塩化ビニル管
塩化ビニル管は、主に下記の4種類あります。
VP管
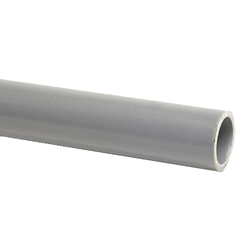
VU管
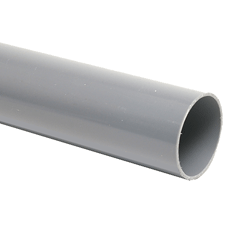
HIVP管
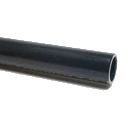
HTVP管

□ VP管(塩化ビニル厚肉管)
主に屋内の給排水配管、エアコンのドレン排水で使用されます。
□ VU管(塩化ビニル薄肉管)
主に屋内の排水、屋外埋設排水配管、エアコンのドレン排水で使用されます。
VP管よりも肉厚が薄いです。
□ HIVP管(耐衝撃性塩化ビニル管)
衝撃に強く、主に屋外埋設給水配管で使用されます。
□ HTVP管(耐熱塩化ビニル管)
耐熱性があり、主に屋内の給湯配管で使用されます。
熱伸縮が大きいので、伸縮対策が必要です。
■ 塩化ビニルライニング鋼管
塩化ビニルライニング鋼管は、塩化ビニル管の外側が鋼管で被覆されたパイプで、主に下記の6種類あり
ます。
SGP-VA管
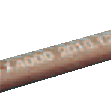
SGP-VB管
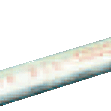
SGP-VD管
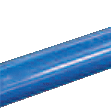
HTLP管
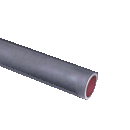
DVLP管
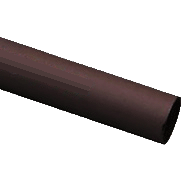
WHTLP管

□ SGP-VA管
SGP-VB管よりも安価で、主に屋内の給水配管で使用されます。
加工に技術が必要なので、小口径の給水は、架橋ポリエチレン管で行う事が多くなってきました。
外面はダークブラウンで塗装され、内面はグレーの塩ビです。
□ SGP-VB管
主に屋内の給水配管で使用されます。
SGP-VA管と同様で、加工に技術が必要なので、小口径の給水は、架橋ポリエチレン管で行う事が多くなっ
てきました。
外面はシルバーやライトグレーで塗装され、内面はグレーの塩ビです。
□ SGP-VD管
主に屋内外のコンクリート内、道路内の給水配管で使用されます。
外面はブルーで塗装され、内面はグレーの塩ビです。
□ HTLP管(耐熱塩化ビニルライニング鋼管)
主に屋内の給湯配管で使用されます。
加工に技術が必要なので、銅管よりも使用頻度は少ないようです。
外面はダークブルーなどで塗装され、内面はレッドの塩ビです。
□ DVLP管(排水用塩化ビニルライニング鋼管)
主に屋内の排水配管で使用されます。
外面はダークブラウンで塗装され、内面はグレーの塩ビです。
□ WHTLP管(内外面耐熱塩化ビニルライニング鋼管)
主に屋外埋設給湯配管で使用されます。
HTLP管の外面にアイボリーの塩化ビニル管で被覆されたパイプです。
■ 銅管
銅管は、銅製のパイプで、主に下記の2種類あります。
銅管

被覆銅管
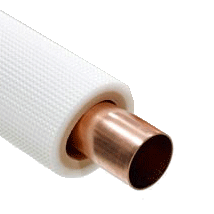
□ 銅管
主に屋内の給湯配管で使用されます。
腐食が発生する場合があり、最近は使用頻度が少なくなってきました。
□ 被覆銅管
主に屋内の給湯配管で使用されます。
銅管の外側にホワイトの樹脂で被覆されています。
■ TMP管(耐火二層管)
主に屋内の排水管で使用されます。
耐火性があるので、防火区画貫通部分で使用される事が多いです。
VP管、VU管の外側に石綿で被覆したものです。
耐火二層管

■ 架橋ポリエチレン管
主に屋内の給水・給湯配管で使用されます。
施工性や加工性が良いので、最近は使用頻度が高くなってきました。
架橋ポリエチレン管よりも以前に開発されたポリブテン管と特徴が似ています。
外面は、ブルー(給水)又はレッド(給湯)で、内部は透過白色です。
架橋ポリエチレン管
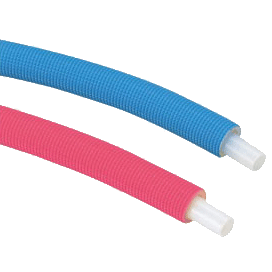
■ ポリブテン管
主に屋内の給水・給湯配管で使用されます。
施工性や加工性が良いので、使用頻度が高いです。
ポリエチレンやポリプロピレンと同じ系統のポリブテンを材料とした合成樹脂管です。
カバー付では、外面は、ブルー(給水)又はレッド(給湯)で、内部はアイボリーです。
ポリブテン管
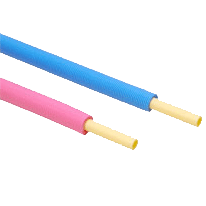
■ ステンレス鋼管
他の材料よりも高価で、主に公共施設で採用される場合が多いです。
環境面を考慮し、最近は一般住宅でも採用頻度が高くなっています。
サビに強く、衛生的です。
最近、ステンレス鋼管の外側にポリエチレンを被覆して結露を防止するタイプが開発されたようです。
ステンレス鋼管

■ SGP管(炭素鋼鋼管)
主に屋内のガス配管で使用されます。
錆止めの為に亜鉛メッキを施した白ガス管、亜鉛メッキを施さない黒ガス管があります。
炭素鋼製のパイプで、錆に弱いので、水道管や排水管では、ほとんど使用されなくなりました。
SGP管

■ PE管(ポリエチレン管)
高密度ポリエチレン製のパイプでは、主に給水・排水配管用で使用されます。
中密度ポリエチレン製のパイプでは、ガス配管用で使用されています。
施工性、可とう性、耐久性、耐薬品性に優れています。
ガス用ポリエチレン管は、グリーンから(1998年以降は)イエローに変更されています。
PE管(給排水用)

PE管(ガス用)

■ ガス用ステンレス鋼フレキシブル管
主に屋内の壁内、床下などの隠ぺい部分のガス配管で使用されます。
ステンレス鋼(SUS304)製のパイプで、耐食性や耐久性に優れています。
内外面ともアイボリーです。
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管

■ 電線用鋼管
電線用鋼管は、主に下記の3種類あります。
G管
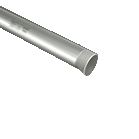
C管
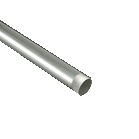
E管
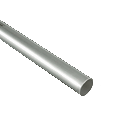
□ G管(厚鋼電線管)
内外面に溶融亜鉛メッキを施した肉厚な金属管です。
耐候性と強度を兼ね備え、主に屋外の電気配管で使用されます。
□ C管(薄鋼電線管)
G管と比較して肉薄な金属管です。
耐候性が良くないので、主に屋内の露出場所や天井裏の電気配管で使用されます。
□ E管(ねじなし電線管)
ねじきりをしない前提で、C管と比較しても更に肉薄な金属管です。
耐候性が良くないので、主に屋内の露出場所や天井裏の電気配管で使用されます。
■ VE管
塩化ビニル製の電線管です。
熱や直射日光に弱いので、主に屋内や埋設電気配管で使用されます。
VE管
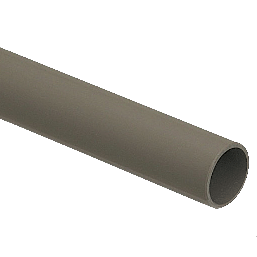
■ 合成樹脂製可とう電線管
合成樹脂製可とう電線管は、主に下記の3種類あります。
PF管

CD管

FEP管

□ PF管(合成樹脂製可とう電線管)
合成樹脂製の電線管です。
自由に曲げる事が出来るので施工性が良く、又、耐久性や耐食性も良いです。
自己消火性があるので、屋内の天井裏や壁内の他、屋外でも使用されます。
但し、常時直射日光が当たり温度変化が著しい部分は、(単層構成のPFS管に対して)複層構成のPFD管を
使用します。
□ CD管(合成樹脂製可とう電線管)
(PF管と同様で、)合成樹脂製の電線管です。
自由に曲げる事が出来るので施工性が良く、又、耐久性や耐食性も良いです。
自己消化性がないので、コンクリート内に埋設するか、屋内の天井裏や壁内(但し、IV線が入る場合は不可)
で使用されます。
耐候性がほとんどないので、屋外露出での使用は控えます。
PF管と区別する為に、オレンジに着色されています。
□ FEP管(波付硬質ポリエチレン管)
合成樹脂製の電線管です。
自由に曲げる事が出来るので施工性が良く、又、耐久性や耐食性も良いです。
内径30㎜以上の管で、主に屋外の埋設配管で使用されます。
省エネ意識の高まりや以前より価格が安くなり、LEDランプの使用が増えていますが、住宅で使用されてい
る一般的な照明ランプについてまとめてみました。
|
ランプの種類
|
特徴 |
寿命の目安 (時間) | ||
|
白熱 電球
|
一般 電球 |
|
スイッチを入れるとすぐに点灯します。 ON、OFFを頻繁に行う場所に適しています。 調光器との併用で、調光が自在です。 消費電力が大きく、ランプ寿命が短いです。 |
1,000 |
|
ボール 電球 |
|
2,000 | ||
|
ミニクリプトン 電球 |
|
2,000 | ||
|
ハロゲン 電球 |
|
3,000 | ||
|
蛍光 ランプ
|
電球形 蛍光ランプ |
|
スイッチを入れて点灯するまでやや時間がかかります。 長時間連続して使用する場所に適しています。 調光用蛍光ランプを使用すれば、調光は可能です。 消費電力は、白熱電球と比較すると小さく、ランプ寿命が長いです。
|
6,000 |
|
コンパクト形 蛍光ランプ |
|
5,000 | ||
|
環球形 蛍光ランプ |
|
6,000 | ||
|
直管形 蛍光ランプ |
|
10形 : 6,000 20形 : 8,500 40形 : 12,000 | ||
|
LEDランプ
|
|
スイッチを入れるとすぐに点灯します。 ON、OFFを頻繁に行う場所や、ランプ交換が難しい部分に適しています。 調光タイプを使用すれば、調光は可能です。 消費電力は、蛍光ランプと比較すると小さく、ランプ寿命が長いです。 |
ランプ交換型20,000 取替器具一体型 40,000 | |
畳は、表面(畳表)、内部(畳床)、縁(畳縁)で構成されています。
ここでは、それぞれの代表的なものを記載します。
■ 畳表
畳の表面部分を示し、主に下記の5種類あります。
□ 普通イ草表
(断面が丸形の)普通イ草を使用した畳表で、昔から一般的に使用されている畳です。
□ 琉球表
(断面が三角形の)七島イ草を使用した畳表で、普通イ草よりも目が粗くて曲げに強く、主に縁無し畳に使用
されます。
□ 目積表
普通イ草を使用して、琉球表と同様な織り方をし、主に縁無し畳を作る場合に使用されます。
□ 龍髭表
水洗いと天日乾燥を繰り返し、渋茶色をしています。
主に床の間で使用されます。
□ 和紙表
(イ草ではなく)和紙を使用した畳表で、細かくした和紙を編みこんで使用されます。
■ 畳床
畳の内部を示し、主に下記の3種類あります。
□ 本畳床
ワラを使用した畳床です。
クッション性や吸放湿性が良いが、ダニなどの虫の発生に注意が必要です。
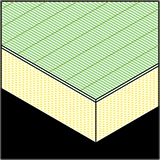
□ ワラサンド畳床
ポリスチレンフォームなどをワラで挟んだ畳床です。
本畳床よりも軽く、断熱性があります。
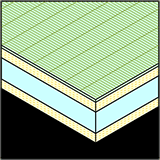
□ 建材床
ワラをまったく使用せず、ポリエチレンフォームなどの建材のみで構成された畳床です。
(バリアフリー用の)薄畳にも対応出来ます。
ワラを使用しないので、ダニなどの虫が発生しにくいです。

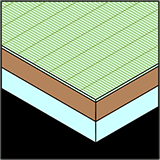
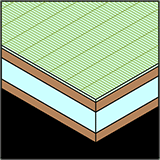
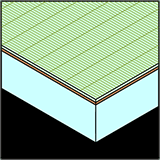
■ 畳縁
綿糸、合成繊維糸、金糸が使用されています。
色、柄は、黒、茶、紺、緑などを基本としてたくさんあります。
冷蔵庫の裏側にコンセントを配置すると、ホコリが積もっていても気づかず、出火してしまう恐れがあります
ので、冷蔵庫の上端より少し(150㎜~200㎜程度)高い位置にした方が良いです。
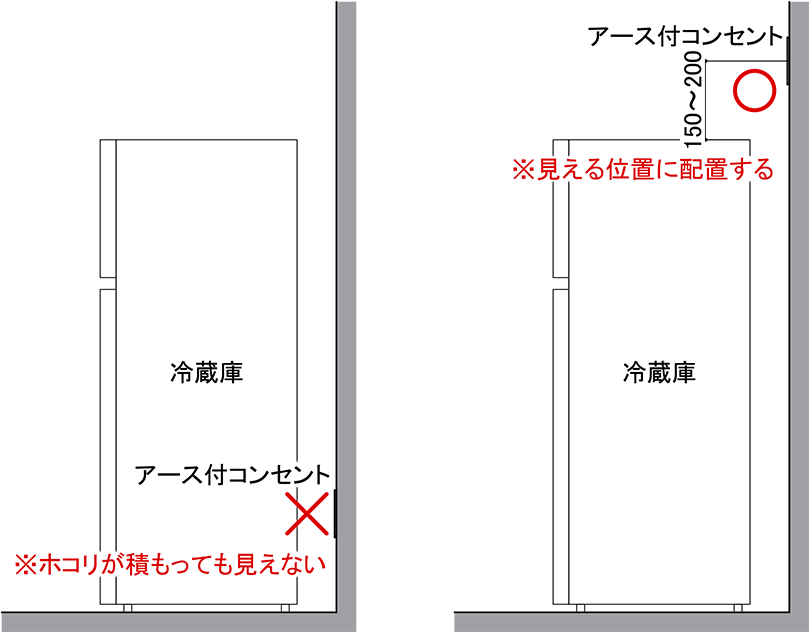
高齢者や足腰の不自由な人にとって、階段を利用するのは負担に感じると思います。
負担軽減のために、ホームエレベーターの設置を検討してみるのも良いかと思います。
□ 定員(積載荷重)と設置スペース
ホームエレベーターの定員(積載荷重)は2人(150㎏)または3人(200kg)が一般的です。
マンションやビルなどのエレベーターと比較すると、省スペースですみます。
ホームエレベーターを設置するのに最低限必要なスペースを下図に示してみました。
メーカーや仕様によって寸法は多少異なりますので、あくまでも参考として見て頂ければと思います。
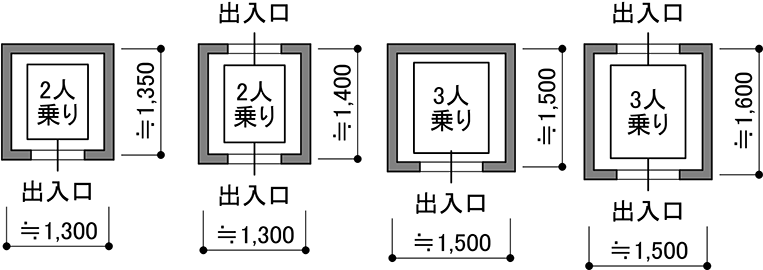
2人乗り1方向出入口 : 1,300㎜×1,350㎜
2人乗り2方向出入口 : 1,300㎜×1,400㎜
3人乗り1方向出入口 : 1,500㎜×1,500㎜
3人乗り2方向出入口 : 1,500㎜×1,600㎜
□ 昇降行程と速度
ホームエレベーターの昇降行程(最下階床面から最上階床面までの高さ)は13m以下で、2~5階建て住宅に
適用されます。速度は、20m/分が一般的で、中層以下のマンションのエレベーターの速度(45m/分又は
60m/分)と比較するとかなりゆっくりです。
□ 価格の目安
ホームエレベーターの価格の目安は、メーカー、仕様、停止ヶ所数などによって異なりますが、本体価格は
、400万円~700万円、ランニングコスト(電気代)は、\400~\800/月、保守点検費は、\50,000~
\70,000/年程度です。
この他に構造補強費や、遠隔監視システムなどを契約すればその分費用がかかります。
□ 安全性や使い勝手
ホームエレベーターには、一般のエレベーターと同様に、扉へのはさまれを防ぐセンサー、停電時に点灯する
停電灯、故障時に最寄り階まで自動運転する機能、ホームエレベーターとメンテナンス会社を電話回線で結び
、24時間遠隔監視するシステムなど、安全性や使い勝手の面でさまざまな工夫がされています。
高齢者や足腰の不自由な家族のためにホームエレベーターの検討をしてみたが、設置場所が見当たらなかった
り、費用が高額などの理由でお困りの場合に、階段昇降機を検討しても良いかと思います。
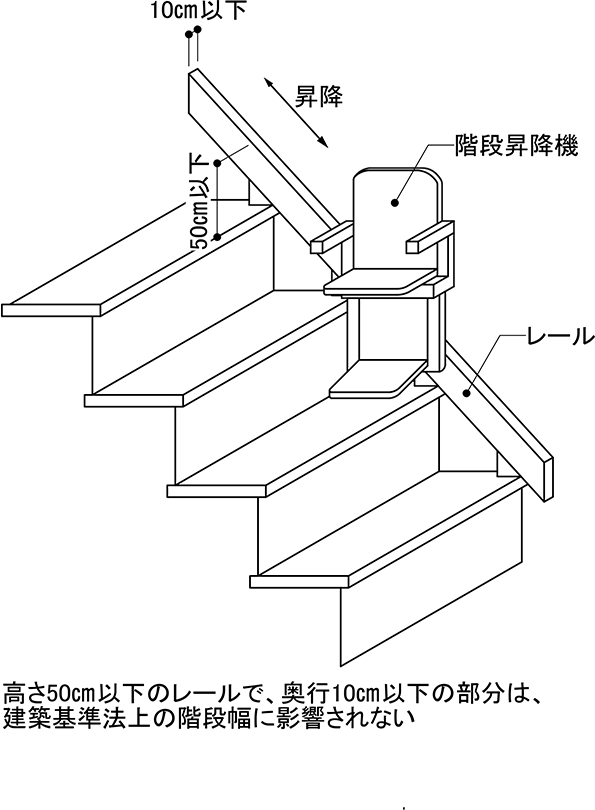
□ 仕様と設置スペース
階段昇降機は、階段に専用レールを設置し、その専用レール沿いに電動で椅子に座ったまま階段を昇降出来る
設備です。
車椅子ごとテーブルに乗って階段を昇降出来る製品もありますが、ここでは住宅の階段で一般的に設置される
椅子式のみを説明致します。
椅子式階段昇降機の椅子の奥行寸法は、一般的に使用時は60㎝程度、未使用時は30㎝程度に折りたたむ事が
出来ます。
屋内外共に、直線階段だけではなく、曲がり階段に対応出来るタイプがあります。
□ 定格速度
定格速度は、9m/分以下で設定され、ホームエレベーターの半分程度の速度です。
階段昇降機を使用中に、リモコンでスピード調節が出来ます。
□ 価格の目安
椅子式階段昇降機の(工事費を含めた)価格は、設置条件や仕様にもよりますが、屋内直線階段用は70~
100万円、屋内曲がり階段用は150万円~200万円程度のようです。
また、屋外用の場合は、屋内用と比較すると価格が上がります。
□ 階段昇降機採用にあたって
階段昇降機は、メリットだけではなく、デメリットもあります。
1. 昇降時に利用者が恐怖心を抱く場合があります。
2. 車椅子使用者の場合、介助者が到着フロアーに車椅子を持ち運ぶか、車椅子を2台用意する必要がありま
す。
これらのデメリットをふまえて、採用については慎重な検討が必要です。
自然素材の家を建てたい!という建築主さんはたくさんいらっしゃいます。
しかし、どのような自然素材があり、それぞれどのような特徴があるのか以外と知られていません。
ここでは、床で使用される一般的な自然素材をご紹介します。
□ 無垢フローリング

無垢フローリングは、天然木から取り出された単板の事です。
一般的に厚さ15㎜以上のものが多く、材種はさまざまで、調湿性があります。
裏地に合板を使用しない為伸縮が大きく、板が反ったり、板間に隙間が出たりする場合があります。
塗装をする場合、木の呼吸を妨げないように、自然塗料を使用する事をお勧めします。
□ 籐

籐は、断熱性があり、素足の感触も良く、水にも強いので、主に洗面所や脱衣室などで使用されます。
また、弾力性や耐久性があり、椅子や家具などでも使用されます。
水分を含むと伸びます。
□ 竹

竹は、硬さがあり、反りにくい為、洗面所や脱衣室などの水廻り空間をはじめ、さまざまな空間で使用されま
す。
竹タイルは、断熱性があり、素足の感触が良く、洗面所や脱衣室などで使用されます。
竹を加工してつくった竹フローリングは、見た目の美しさからリビングなどでも使用されます。
また、耐久性や柔軟性があり、垣根や民芸品などでも使用されます。
竹タイルは、水分を含むと伸びます。
□ サイザル麻

サイザル麻は、繊維が強靭でありながら、柔軟性や耐久性に優れています。
ケバケバが強いので、素足歩行する場所はあまりお勧め出来ませんが、素足歩行する以外の幅広い用途の部屋
で使用されています。
水分を含むと縮みます。
□ ココヤシ
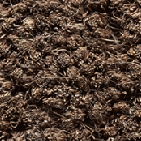
ココヤシは、耐水性や耐久性に優れています。
ケバケバが強いので、素足歩行する場所はあまりお勧め出来ませんが、素足歩行する以外の幅広い用途の部屋
で使用されています。
水分を含むと伸びます。
□ コルク

コルクは、コルク樫という表皮が原料で、床材としてはタイルやフローリングで使用されます。
断熱性があり、フローリングのようなヒヤッとした感覚がないので、素足の感触が良いです。
ワインの栓に使用されるくらい耐水性があり、また、滑りにくいので、キッチン、浴室、脱衣室などの水廻り
で使用されます。
クッション性があり表面が柔らかい反面、動物などの引っ掻き傷に弱いのと、直射日光を長時間浴びると色が
抜け、白っぽく変色してしまう事が注意点です。
□ 畳
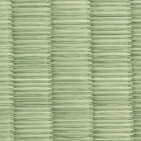
畳はさまざまな種類(D-010. 畳の種類参照)がありますが、日本で昔からある本畳は、畳表に普通イ草、
畳床にワラを使用した自然床材です。
クッション性や断熱性が良く、また、肌触りも良いため、直接寝そべったり座ったり出来ます。
一方、ダニなどの虫が発生しやすいので、畳床に建材を使用した化学畳が多く使用されるようになりました。
□ リノリウムシート
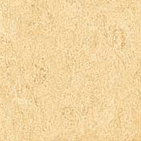
リノリウムシートは、一見すると塩化ビニール製シートのように見えますが、亜麻仁油、松ヤニ、木粉、コル
ク、石灰岩、顔料、ジュートなどの自然素材でつくられた床材です。
材料に含まれる亜麻仁油は、抗菌性があり、昔から病院や学校などで使用されてきました。
自然素材の家を建てたい!という建築主さんはたくさんいらっしゃいます。
しかし、どのような自然素材があり、それぞれどのような特徴があるのか以外と知られていません。
ここでは、壁で使用される一般的な自然素材をご紹介します。
□ 漆喰(しっくい)
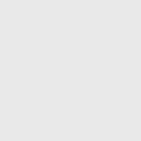
漆喰は、消石灰を主成分とし、砂や糊などを混合し、ひび割れ防止の為に、麻、すさなどの繊維質を加えて水
で練って出来たものです。
耐火性、耐久性に優れ、また、調湿機能もあり防カビ効果が高いです。
空気中の二酸化炭素に反応し、石灰石の成分に戻り硬化するので、耐水性にも優れています。
□ 珪藻土(けいそうど)

珪藻土は、海や湖で生息していた珪藻という植物性プランクトンの死骸が長年に渡り堆積して出来た粘土状の
泥土です。
多孔質で調湿性に優れ、ホルムアルデヒドの吸着・分解効果もある事から内装用の壁材として人気が高いで
す。
珪藻土のみでは固まらず、セメントなどの凝固材を混合していますが、メーカーによってその比率が異なり、
珪藻土本来の効果が少ない製品もあるので注意が必要です。
□ 聚楽壁(じゅらくかべ)
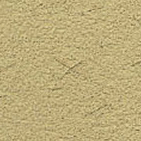
聚楽壁は、本来、上塗りに京都西陣の聚楽第跡地付近から産出される土を使用した土壁の事を言います。
京都を代表する仕上用の土壁で、耐火性に優れ、数寄屋建築や茶室の壁に使用されています。
しかし近年は、細かい粒子状の仕上表面の事を指す事が多くなっています。
□ 大津壁(おおつかべ)
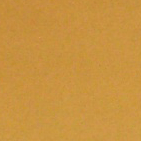
大津壁は、上塗りに消石灰と色土を混合し、ひび割れ防止の為に、麻、すさなどの繊維質を加えて水で練って
出来たものです。
平滑な仕上面が漆喰と似ており、漆喰の白(色つきもある)に対して、大津壁は(主に黄色系の)色が付いて
いる事で、見分けられます。
滋賀県大津付近で産出される色土を使用したので名前の由来です。
□ シラス
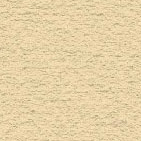
シラスは、マグマが噴火と同時に冷やされて火砕流となって堆積し粉末となったもので、鹿児島県から宮崎県
南部にあるシラス台地が産地です。
マグマの超高温で焼成された無機質セラミック物質で、多孔質でシラスの主成分である珪酸やアルミナにより
調湿機能や消臭機能が優れています。
□ ケルザイム
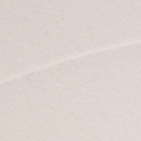
ケルザイムは、海洋藻類が化石となって堆積したもので、アメリカネバタ州の一部の地域が産地です。
主にカルシウムとミネラル(ケルザイム)が含まれ、調湿機能や消臭機能に優れた内装用の健康塗り壁として
製品化されています。
水で希釈し吹付け施工をする事で、コテ塗りと比較してコストダウンが可能です。
また、自然栄養補助食品、有機土壌改良剤、スキンケア製品としても使用されています。
□ ケナフ壁紙

ケナフは、1年草で春に種をまき、秋には太さ3~4㎝、高さ3~4mに成長するので、環境負荷が少ないエコ
素材です。
木に近い性質を持っており、紙や繊維をつくる事が可能です。
ケナフ壁紙は、表層に撥水樹脂やフィルムを使用し、耐久性を高めています。
□ 和紙壁紙
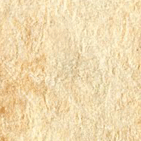
和紙を使用した壁紙で、塗り壁と比較すると、ローコストで和の雰囲気をかもしだす事が出来ます。
和紙と言えば燃えやすいイメージがあると思いますが、不燃又は準不燃製品がほとんどです。
□ 織物壁紙
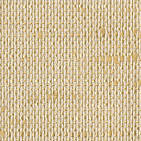
さまざまな糸で織りなされた壁紙で、その素材感によって、温かみのある雰囲気をつくりだす事が出来ます。
不燃又は準不燃製品がほとんどです。
□ コットン壁紙

コットン素材を使用した壁紙で、その素材感によって、柔らかい雰囲気をつくりだす事が出来ます。
準不燃製品がほとんどです。
自然素材の家を建てたい!という建築主さんはたくさんいらっしゃいます。
しかし、どのような自然素材があり、それぞれどのような特徴があるのか以外と知られていません。
ここでは、D-014、D-015で記載した以外で使用される一般的な自然素材をご紹介します。
■ 接着剤
□ にかわ
にかわは、古代エジプトの時代から使用されていたとされ、動物の皮や骨などの結合組織の主成分であるコラ
ーゲンを加熱してできたゼラチンです。
化学物質を含まず、接着強度が大きいので、特に自然素材にこだわる人にお勧めです。
■ 塗料
□ 植物性オイル
植物性オイルは、自然塗料の代表的なもので、亜麻仁油、桐油、ひまわり油などを使用してつくられていま
す。
無垢フローリングなどの呼吸する素材に塗装するのに適しています。
顔料や染料を混ぜた着色塗料もあります。
□ ワックス
ワックスは、蜜蝋(みつろう)などを使用してつくられています。
蜜蝋は、ミツバチが巣をつくる時に分泌するものです。
仕上後、艶出しや表面保護の目的で塗装します。
□ 漆(うるし)
漆の樹液を使用してつくられています。
塗膜が強靭で、年月が経つほど艶が増してきます。
日本独自の塗料で、昔から家具や器で使用されてきました。
□ 柿渋(かきしぶ)
柿渋は、熟す前の柿の汁を発酵してつくられています。
塗り重ねる事によって防水効果が期待出来ます。
■ 断熱材
□ セルロースファイバー

セルロースファイバーは、古新聞を細かくし、ホウ酸を混合して断熱材として吹付けます。
隙間なく施工出来るので、断熱効果は高いです。
まれに、印刷のインク(有機塗料)が室内に揮発し、アレルギーを起こす事があります。
□ 炭化コルク

炭化コルクは、コルクを炭化させたもので、隙間なく施工すれば、かなりの断熱効果を期待出来ます。
また、調湿機能があり、結露の発生を抑制します。
コストが高いのが難点です。
□ 羊毛
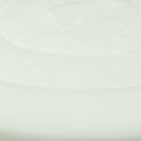
羊毛は、抗菌機能や消臭機能があります。
隙間なく施工出来るので、断熱効果は高いです。
防虫剤として、岩塩を食塩に精製する際に抽出した非塩素系ホウ酸を使用しています。
地盤は、家を支える重要な部分です。
基礎形式(D-004. 住宅基礎の種類参照)や、地盤改良の必要性等を決定する為に、地盤調査は必要です。
また、施工会社が住宅瑕疵担保保険(C-005. 住宅瑕疵担保履行法とは参照)に加入する為にも地盤調査を
する必要があります(※)。
土地を購入する前に売主である不動産屋さんに地盤の状況を確認しつつ、自分で地盤状況をある程度チェッ
ク(B-009. 自分で簡単に地盤を確認する方法参照)した上で、土地を購入するか判断する事が重要です。
そして、土地を購入後、ある程度プランが決まった段階で、実際に地盤調査を行います。
地盤調査の方法は様々ありますが、木造2階建て住宅で一般的に行われているのは、SWS試験(スクリュー
ウエイト貫入試験)です。
(※)木造2階建て以下で保険法人による現場チェックシートの結果により、地盤調査を行う必要が無い場
合もあります。
1. 地盤調査の目的
地盤の地耐力と不均質性を調べる。
地盤調査の結果から基礎形式や地盤改良の必要性を判断する。
2. 調査費用
5万円~10万円/宅地 程度
3. 調査箇所数
建物の4隅付近を含めた4点以上
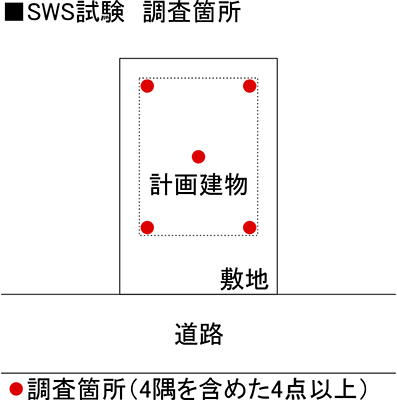
4. 計測方法
おもりを載せたロッド(鉄の棒)が自沈しないかどうかを確認する。
自沈しない場合、回転させて1m貫入するのに要した半回転数をもとに地盤の支持力を評価する。
地下水位は、試験孔を利用して測定が可能である。
土質の判別は、ロッドに付着した土や、音、感触などで調査員が推定する。
(写真1)SWS試験測定器(自動式)
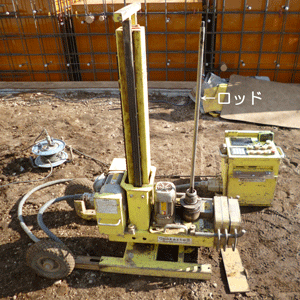
(写真2)水位計
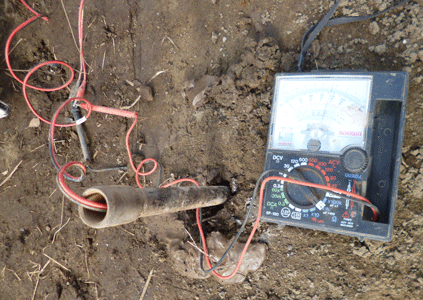
5. 調査結果から求められるもの
a. 基礎形式(D-004. 住宅基礎の種類参照)
地耐力によって適切な基礎の種類が求められる
b. 地盤改良の必要性
各調査箇所(建物4隅を含めた4点以上)を比較し、地盤の不均質性が著しい場合は、地盤改良が必要とな
る。
また、木造住宅の荷重が地中の変形に及ぼす範囲は、基礎下5m迄といわれており、その範囲で自沈層が多く
存在するのであれば、地盤改良が必要と考えた方が良い。
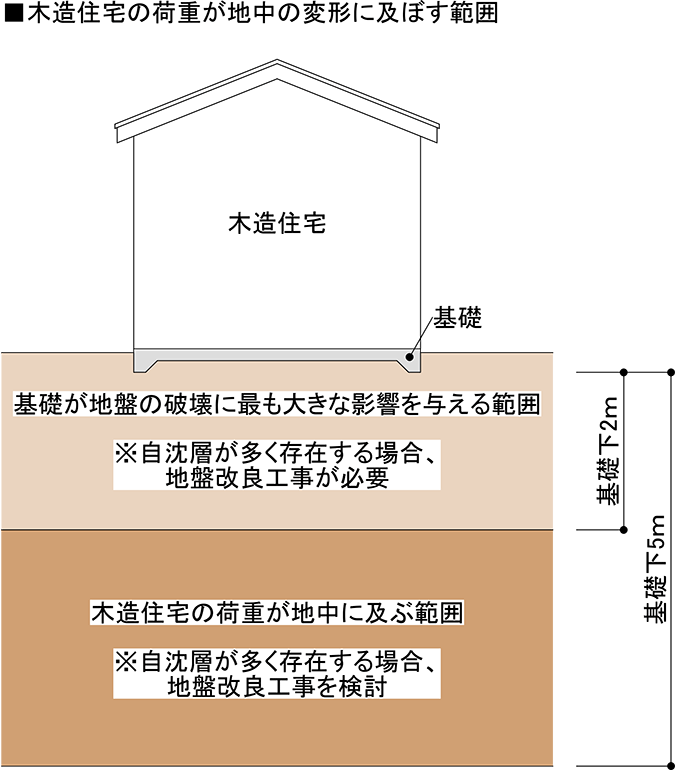
地盤の地耐力、不均質性、地質等に外的要因(建物荷重、自然災害等)が加わり、様々な現象が発生します。
主な3つの現象を以下で述べます。
1. 不同沈下
地盤の地耐力不足等が原因の傾斜角タイプと、地盤の不均質性が原因の変形角タイプがある。
変形角タイプの場合は、重大な損害を受けやすい。
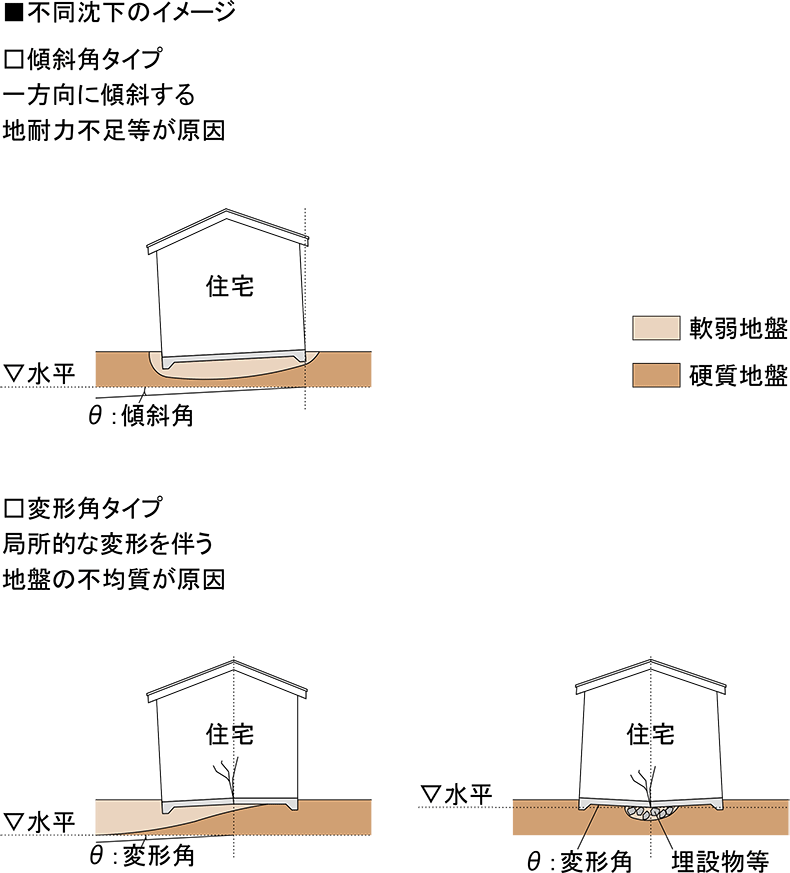
2. 圧密沈下
水分を多く含んだ粘性土で発生し、建物の荷重がかかると水分が排出され、地盤が沈下する事。
土の水分量の違い等により、不同沈下になりやすい。
木造住宅であれば、SWS試験で自沈層の有無や厚さを確認する。
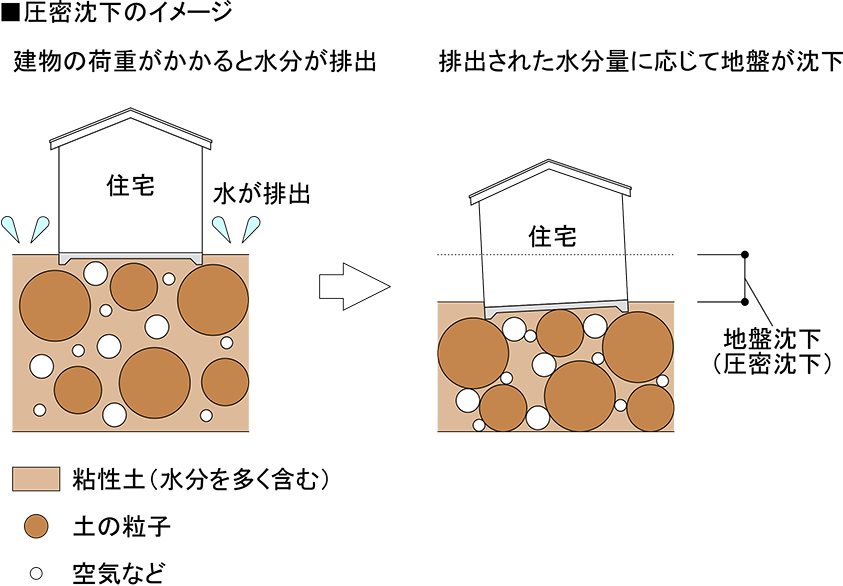
3. 液状化現象
地下水位が(3mより)浅く、砂質地盤に発生しやすい。
水を含んだ砂質地盤が、地震時に液体のように噴き出す現象の事。
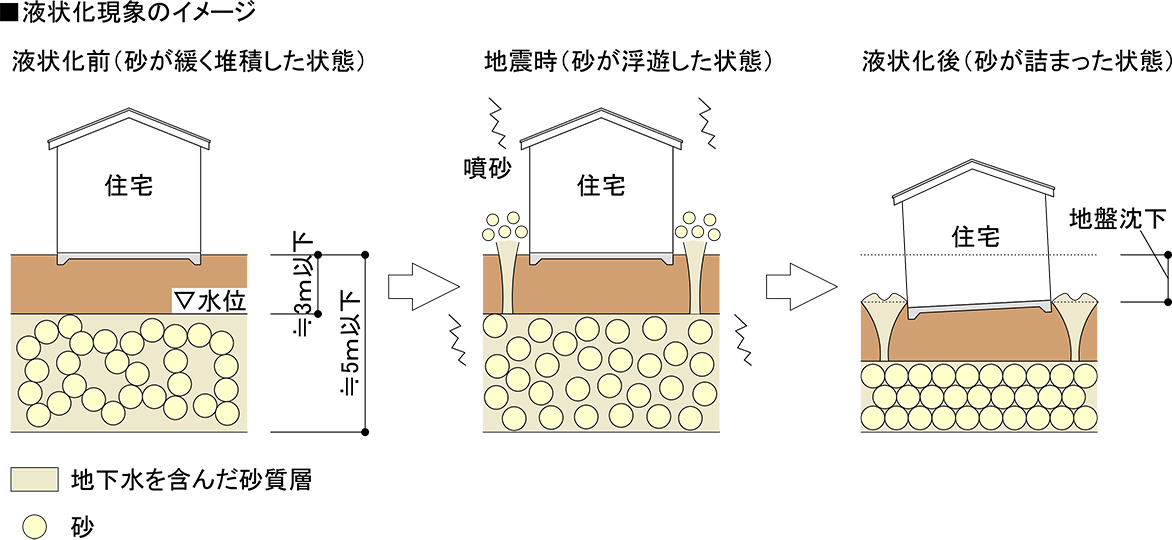
地盤改良は、様々な工法があり、また、新型の工法が開発されています。
ここでは、従来から行われてきた代表的な工法(3種類)を紹介します。
1. 表層改良工法
軟弱な地盤(N値3未満)が、地表から2m以内の場合に適用される。
軟弱地盤の土とセメント固化材を混ぜて、化学反応や転圧する事で、地盤の支持力を上げる方法。
2. 柱状改良工法
軟弱な地盤が地表から2m~8m程度に分布している場合に適用される。
地盤を掘削し、セメント系固化材を注入して柱状のコラムをつくり、建物を支える方法。
3. 鋼管杭工法
軟弱な地盤を補強するのではなく、硬い地盤(支持層:N値15以上かつ2m厚以上程度)まで鋼管を挿し込ん
で、建物を支える工法。
支持地盤の判断基準については、鋼管の種類等により異なる為、地盤改良会社にお問い合わせ下さい。

大きく開放的な窓の先にある緑豊かな中庭を、リビングでくつろぎながら眺めるって、多くの人が快適と感じ
るのではないでしょうか?
そんな快適な空間も、夜になると中庭は見えず、見えるのは窓に映る自分の姿と室内空間だったなんて事あり
ませんか?
こうなるのは、室外よりも室内の方が明るくなる事で、窓にミラー効果が発生するからです。
夜でも窓の先にある中庭の景観を楽しむ為には、室外を照明で明るくし、室内を調光によって暗くする事で解
決します。
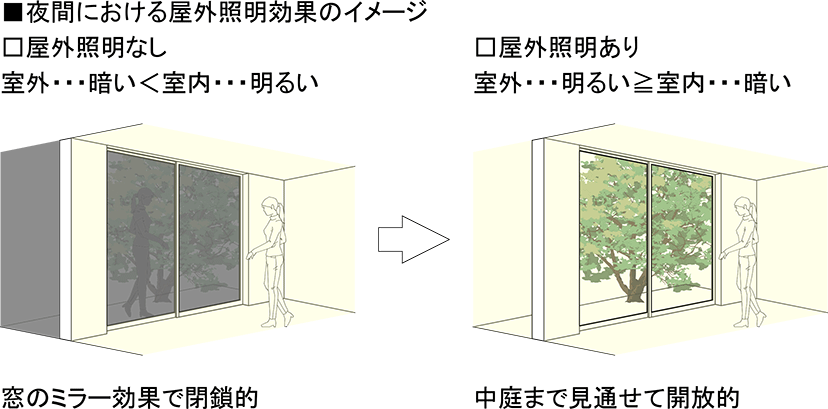
軒のある家、軒のない家にはそれぞれメリットがあります。
それぞれを簡潔にまとめてみました。
■ 軒のある家のメリット
1. 夏の日光を遮る
2. 雨から外壁を守る
3. 雨を窓から室内に吹き込みにくくする
■ 軒のない家のメリット
1. 建築物を敷地境界線に近接出来る(各高さ制限はクリアする必要はあります)
2. 軒のない分、コストが安くなる
3. デザインがシンプルになる